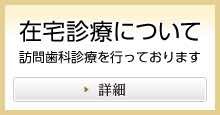親知らず抜歯後の注意事項
傷口をしっかり閉じて縫うと腫れが大きくなる傾向があります。ですから、出血しやすいなどの事情がなければ傷口は緩めに縫ってあります。
したがって、傷を保護するためにも抜歯後しばらくは口を大きく動かさない(例えば口を何度もゆすぐ、長話をするなど)、傷を触らないことが大事です。
傷口を塞いでいる血の塊(血餅:けっぺい)がとれてしまうと、骨が露出するドライソケットと呼ばれる状態に陥り、強い痛みが数週間程度継続します。
抜歯当日
帰宅時にガーゼを噛んでもらい圧迫止血を行います。20-30分程度噛んだらガーゼは捨ててください。
出血が多くなりますので、抜歯当日の運動、長風呂、飲酒は控えてください。
タバコは傷口の治りを悪くするので1週間は控えておいてください。
抜歯後2-3時間で麻酔が切れてきます。処方した鎮痛薬を飲んでください。
鎮痛薬は効くのに少し時間がかかりますので、痛む前に飲むことをおすすめします。
当日は冷やしてもらうと痛みが少なくなります。
翌日以降は冷やすと傷口の治りが悪くなりますので、冷やさないようにしてください。
食事に制限はありませんが、とがったもの(揚げ物やおせんべいなど)、辛いもの、酸っぱいものは傷口にしみるのでやめておいたほうが良いでしょう。
お粥、うどんなど柔らかいものを、抜歯したのと反対側の顎で食べるのが無難です。
歯磨き粉もしみることがありますので、水で磨いてもらう方が良いです。傷口を歯ブラシで磨いてしまうと痛いですし、出血もしますから歯ブラシは当てないように気をつけてください。
抜歯2-3日後
だんだん腫れが強くなってきます。2-4日程度が腫れのピークです。とくに下顎の抜歯後はお多福のようになってしまうこともあります。
ですから、人前で話をする、友達とご飯を食べるなどの予定は入れないことを強くお勧めします。
腫れによって口が開けにくくなることもありますが、徐々に戻っていくので安心してください。
抜歯7日後以降
一般的に傷口は落ち着き、腫れも引いてきます。
抜糸のタイミングもこのあたりです。糸が勝手にほどけることもありますが、基本的に問題はありません。